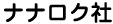第3回 写真と詩の「匂い付け」
ピッタンコのものは、置かない
たくさんの著作がある谷川さんですが、1編の詩で1冊の本をつくるのは、実は今回が初めての試み、とのこと。今回は、写真詩集『生きる』における写真の選び方、詩との距離感などについてのお話です。
【谷川】
じゃあこのへんで、写真詩集『生きる』の話をしましょうか。
今回のように、1ページに1行で、ことばの対面に写真がある、
っていう形の本は、僕も初めてなんですよ。
松本さんのところには、どういう形で写真の依頼が来たの?
【松本】
まず、「生きる」という1編の詩で1冊の本にしたい、ということと、
詩の1行に対して、1つ写真がくるようにして撮りましょう、
と編集の人と最初の打ち合わせで話をしました。
【谷川】
僕がすごくおもしろいと思ったのは、写真の選び方。
普通だと、詩の行にくっつく写真を当てることが多いじゃないですか。
たとえば、「アルプス」という言葉に対して、
「アルプスがあります」みたいな写真を当てる、
カレンダー的な発想というか……。
【松本】
そうですね。
【谷川】
今回の写真はそれとまったく違う発想ですよね。
言葉と写真のあいだの結びつき、
距離感みたいなものがすごくおもしろかった。
松本さんは、本能的にああいう写真を選んでいるの?
それとも意識して?
【松本】
半分は本能ですね。
最初にお話をいただいたときに、谷川さんが「自由に撮っていい」と
言ってくださったので、ほとんど気負いなく撮れたんです。
「生きる」という詩の全体のイメージは
いつも頭の片隅にあったんですけれども、
この行に対してこういう写真を撮ろう、
というのは一切考えずに撮りました。
【谷川】
たしかに、そんな感じですね。
【松本】
実際に約1年間かけて何百枚という写真を撮りました。
とりあえず撮るだけ撮って、
そこからいいものを200~300枚選んで一回出して、
そこからさらに絞り込んでいくという作業をしたんですね。
そのとき、「ピッタンコのものを置かないようにしよう」ということには
すごく気をつかいました。
もしそういう作り方をするなら、私ではなくて、
もっとフォトドキュメンタリーとか、
ネイチャーフォトをやっている人が
この仕事をするべきだろうと思ったので。
私の写真だったら、「生きる」の詩に出てくるものを
そのまま再現するというよりは、
「生きる」とか「二十億光年の孤独」とかを読んで
育った子どもが見てきた世界、というものを
なんとなく出していければいいなあ、
と思って写真を選びました。
それは自分でも成功したと思います。

「含意的」な写真
【谷川】
「連句」っていう、俳句で5・7・5・7・7とつなげていく
伝統的な詩歌の形式があるんだけれど、
それの現代的な形で「連詩」っていうのがあるんですね。
3行とか5行ずつ違う詩人が書いていって、
それをつなげてひとつの詩をつくる、というものなんですけれど、
そのときに、「匂い付け」っていうのがあるんですよ。
【松本】
「匂い付け」?
【谷川】
そう。連句の場合にはそれがすごく大事なんです。
前の句と次の句がすごくくっついてしまっていることを、
「ベタ付け」というんですが、これは絶対ダメなのね。
連詩でも同じで、
前の詩を何らかの形で受けなければならないんだけれど、
直接的なくっつき方ではダメで、本当に微妙な距離で
違うものを出さなければならない、
それを「匂い付け」って言うんです。
松本さんの写真にも、そういうものを感じました。
なんか、詩とすごく微妙なところで呼応しあっているんだけれど、
それは言葉では説明できません、みたいなね。
【松本】
そうですね。私は「微妙」とか「曖昧」とか
そういうものをすごく大事に思っているので、
それは意識していると思います。
「こういうものを撮りたい」というよりは、
「雰囲気」とか「ムード」「時間帯」というのを
大事に見ているような気がしますね。
【谷川】
言葉でいうと、「明示的」と「含意的」っていう言葉がありますよね。
「明示的」というのは、要するに辞書に載っているような、
はっきりと「こういう意味です」ってひとつで指させるようなもので、
「含意的」というのは曖昧で、いろんなニュアンスが含まれていて、
その言葉によっていろんな連想が広がるみたいなことですが、
そういう意味では、松本さんの写真はすごく「含意的」な写真ですよね。
【松本】
そうですね。
【谷川】
だから、きっとすごく詩と相性がいいんですよ。
【松本】
詩が好きだからですかね(笑)。
谷川さんの詩はもちろんなんですけれど、
詩の世界が好きなんだと思います。
【谷川】
写真っていうのは、一瞬を切り取りますよね。
そこも詩と似ているんだけれど。
だから今度の本に、「carpe diem」っていう
ラテン語のことわざみたいなのを帯に刷ってもらったんです。
【松本】
“この日を捉えよ”。
【谷川】
そう。映画にもなりましたよね、この題名で。
物語っていうのは、歴史や時間に沿って展開していくじゃないですか。
主人公が冒険をしたりしながら成長していくっていうのが、
物語の基本ですよね。
でも詩っていうのは、もう、ぶつ切りなんです。
時間を切り取った断面みたいなところがあって。
僕が写真というものにずっと興味を持ってきたのは、
やっぱり一種の“瞬間芸”みたいなところなんだと思うんです。
写真と詩は、そういう意味でも似ている。
それで結構、写真絵本みたいなのに
積極的に取り組んできたんだと思います。
【松本】
一番最初に書いた写真絵本って、どんなものですか?
【谷川】
たしか『コップ』っていう作品です。
一個のコップを、いろいろな形で写真に撮ってもらったんです。
ただ水を飲む道具というだけでなく、光が当たって虹ができたり、
コップについた指紋から犯罪者を見つけられたりするもの、
そういうコップのいろいろな面を写真で撮ってもらって、
写真だけではわからない部分に言葉をつけていく、
っていうのをやっていたのね。
【松本】
荒木経惟さんとも、一緒に本をつくられてますよね。
【谷川】
荒木さんとの最初の本、『やさしさは愛じゃない』っていうのは、
「アラーキーとなんかやりましょう」という企画だったんです。
さっき連詩の話をしたけれど、詩があって、それに写真で答える、
写真が来て、詩で答える、
みたいなものをやりましょうということだったんですね。
でも、あの人忙しいから、そんなの不可能なんですよ(笑)。
僕は全部、書き下ろしで写真を見て詩を書くんだけれど、
写真見ると、「あれ、これ去年のじゃん!」みたいなのがあって(笑)。
絶対、写真は詩を見て撮ってないわけ。
だけどすごくおもしろくて、被写体になっている女の子を
主人公にして物語風に書いたりしてました。

Profile |
|
|---|---|
|
|