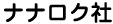第2回 木のカタマリが、生きてるように見える不思議
実は若い頃から写真を撮っていたり、写真とのコラボレーションも多数試みている谷川俊太郎さんと、早くから写真に興味を持ち始めていた松本美枝子さん。今回は、お二人がそれぞれ影響を受けた写真家についてのお話です。
写真家といえば、土門拳!?
【谷川】
写真を始めるときに、ほかの写真家の写真を見ていいなとか、
好きだなと思っていたことはありましたか?
【松本】
ありましたね。
最初に影響を受けたのはわりと早い時期で、
小学校とか中学校の頃なんですけれども、土門拳。
【谷川】
ええ~!
中学校とか小学校のときに、もう土門拳ですか!
【松本】
ええ、なんか「写真家って言ったら土門拳よ~」って、
うちの母親がいつも言っていたので(笑)。
【谷川】
ああ、お母さんの影響か!
でも、一時期そりゃもう、写真家って言ったら土門拳、
っていうのはありましたよね。
【松本】
『筑豊』とか『ヒロシマの子ども』よりも、
私は『古寺巡礼』にすごく影響を受けて。
仏像って、本当はただの木のカタマリなのに、
なんであんなに生きてるみたいに写るのか、
っていうのが本当に不思議で、
子どもの頃からすごく好きだったんです。
【谷川】
僕、土門さんに撮ってもらったこと、ありますよ。
【松本】
ほんとですか!
どんな感じでしたか? 土門さんは。
【谷川】
すごいいばってた。
(会場笑い)
【松本】
いばってそう~(笑)。
【谷川】
なんかもうね、有無を言わせずって感じ。
まあ、俺もすごく若かったから何も言えなかったんだけれど、
こう、座ってるでしょ。
助手に全部いろいろ言いつけて、怒鳴りつけてさ。
で、撮ったものを見せてもらったら、
「あ、やっぱりこれ、他の人が撮るのと違うなあ」
みたいな感じで、すごくて。
完全に真横から撮ってる写真なんですけれどね。
今も大事にとってあります。
【松本】
うらやましい~。
あと、高校生くらいのときに
篠山紀信さんの『サンタフェ』を初めて見て、
それで写真って面白いなと思ったのを覚えています。
篠山さんの写真は、すごく好きですね。
【谷川】
なるほどね。
ほかには、外国の写真家とかは?
【松本】
外国の写真家だと、リネケ・ダイクストラ。
【谷川】
どんな人なんですか。
【松本】
えーと、オランダの女性の写真家です。
私がヨーロッパに旅行に行くと、
必ずリネケの個展をやってるんですよ。
まあ、必ずっていっても3回くらいですけれど。
【谷川】
でも3回は結構すごい確率ですよ。
【松本】
狙っているわけじゃないんだけれど、
行くといつもリネケ・ダイクストラの大規模な展覧会を
パリとかロンドンでやっていて。
すごくいい写真なので、機会があったらみなさんもぜひ見てください。
【谷川】
リネケさんね。覚えておきます。

(c)佐藤理絵
『The Family of man』とダイアン・アーバスの世界
【松本】
谷川さんも、ご自分でいろいろ、写真は撮られていたんですか。
【谷川】
ええ。高校生くらいから自分で写真は撮ってたんです。
リコーフレックスっていう、太平洋戦争後、
いち早くリコーが売り出した、
非常に安い二眼レフがあったんですね。
それがもう爆発的なヒットで、
当時写真を始める人はみんな持ってたんですね。
僕も親に買ってもらって、それで撮ってたんだけれど、
まあ、芸術写真的な意識はなくて、
ちょっと色気がある家庭写真みたいなものを撮ってました。
変な木とか、道とか撮ったりしてさ。
その頃から写真と詩のつながりにはやや興味が出てきて、
300部くらいの自費出版で『絵本』っていう
写真詩集を出したりもしました。
これは全部自分で撮った写真を使っていて、
手ばっかり撮って、それを自分で切り貼りして、
トリミングして貼り付けて作ったんです。
そういう言葉と写真の組み合わせに興味があって、
実はコンテストみたいなものに出したことがあるんですよね~。
【松本】
写真家になりたかったんですか?
【谷川】
なんかほら、これからどうやって食っていこうか、
って考えてるときだから、詩では食えそうもないから、
ちょっと写真も……みたいな感じでね。全然ダメでしたけれど。
その頃はキャノンかなんかの35ミリをちょっと使ってたりしました。
【松本】
影響を受けた写真家というのはいますか?
【谷川】
僕が一番影響を受けたのは、
まずは『The Family of man』っていう写真展。
エドワード・スタイケンっていう、
ローマのキュレーターで写真家だった人が、
まだ冷戦のさなかに、
世界中の写真家から写真をいっぱい集めて、
それを自分で選んで、編集して、
『スイミー』という絵本で有名なレオ・レオー二が
会場構成をして、世界中を回った写真展なんです。
当時、ロシアでもやったということで、すごく有名だったのね。
その写真展が東京でも開かれて、僕はそれを見に行って、
写真というもののすごく広い可能性に、
その時目を開かれましたね。
今でもその『The Family of man』の写真集は売っていて、
すごくいいなと僕は思っています。
それからダイアン・アーバス。
ダイアン・アーバスを見たときに、
『The Family of man』で取り落としているもの、というのが
見えたような気がしましたね。
『The Family of man』っていうのはね、
ちょっと優等生なんですよ(笑)。
もちろん、すごいネガティブな面も写してるんですよ、
人間の喧嘩とか、憎しみとか。
でも全体的にバランス良く世界中のいろんな人種の
生活ぶりが見えるんですね。
それはそれでとても良かったんだけれど、
ダイアン・アーバスを見て、
「そうか……」と感じたところはちょっとありましたね。
Profile |
|
|---|---|
|
|